

合気道だけやっていても、かなりの運動不足かも
いまやオフィスワーカーの多くがモニター越しの仕事で、目と指しか使っていない時間が圧倒的になっています。暇つぶしもスマホだし、なんだったら脳もそんなに使わない生活になっているのかもしれません。
初めて合気道をする人で、体験に来られる方の中には、今はまったく運動していない。
-
2024年12月30日


持たせ方がどうして罠なのか
型稽古で、持たせ方は重要です。
技が成立するから、動きの流れを覚えることができ、効くことを実感できるのです。
でも繰り返しになりますが、持たれ方が変わってしまえば「型通り」では何にも効かないのです。
「ここをこう持て」だけでしか理解できないと、知識のコレクションができるだけです
-
2023年7月21日


『体はゆく』が提起する“できる”の道筋と身体のユルさ
『体はゆく』という本を読みました。驚異的に面白い内容です。
サブタイトル「できるを科学する<テクノロジー×身体>」に惹かれて読んでみたのですが、動く技能を取得するとは、どういうことなのか。
そこをあらためて考えさせられるだけではなく、自分が技を習得するのは、こういうメカ
-
2023年1月19日


満員電車に学ぶ ぶつからない呼吸力の方法
発端は、両手持ちの稽古をしていて「ぶつからない」ように動くと説明していたら、「ぶつかる」が分からないと聞かれたことです。これはどう伝えればいいんだと。
考えてみれば、私も合気道を始めたばかりのころ「ぶつかりをなくす」とか「ぶつからないように動く」とか説明されて、なんのこと???
-
2022年12月24日

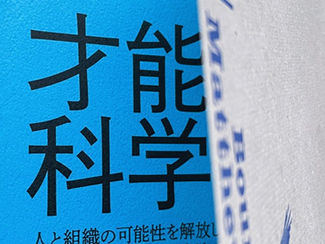
才能は遺伝? それともすべては後天的なのかという問いに
先天的な才能という概念自体が間違いで、ぜんぶ後天的なものだという主張が、異様な説得力をもって迫ってくる本です。
いやいや、そんなことないでしょうよ。
運動能力は千差万別。すぐに出来てしまう人もいれば、なかなか動作を覚えられない人もいる。そう思いながら読んだのですが、なんたって著
-
2022年11月26日


意識を外すためのテクニックとMRの可能性
合気道では、持たれたところを意識するな、と指導されることがあるかと思います。 意識するなと言われても、どうやったら意識しないで動けるのかが、よく分かりませんよね。 以前にも書いていますが、腕を持たれた離脱法の設定。 そこから離脱するには、骨格的な抜き方、テコを使うなどさまざまなコ
-
2022年5月18日


昇級昇段審査の役割って、そこだけじゃないと思う
昇段審査を受けた人は、次の日の稽古で「片手持ち自由技で最初に投げたところぐらいから、頭が真っ白になっちゃいました」と言っていました。すると他の人が「あれは体力的にも大変ですよね」とフォローしました。
すかさず私は、「当たり前じゃん。体力的にも精神的にもキツイの込みで昇段審査だよ」
-
2022年5月12日


合気道の初心者が、技を習得するためのプロセス
少し前に体験をしてくれた人が、稽古が終わってから、「面白かったです。でも、まったく分かりませんでした。一から教えてもらえるんでしょうか?」とおっしゃいました。
そんなの当然です。と答え、ざっと合気道を習得するためのプロセスをお話ししました。安心されたのかどうか、とにかく入会し
-
2022年4月23日


合気道を始めたばかりの人が、とにかく目指した方がいい4つの方向性
合気道初心者が上達するために、いやたぶん楽しんで稽古するためには必要なことですし、何かあったときに、合気道の稽古が役立つためには不可欠なことだと思います。
今回は初心者向けの内容ですので、できるだけカンタンに書いています。
さらに詳しく知りたい方は、リンク先の動画や他の記事に飛
-
2022年2月17日


身体の硬い理由がほとんどメンタルなら、合気道の本質にかかわる問題なのかも
もちろん関節の可動域は人によって様々。運動不足や加齢だけではなく、同じ姿勢でいる時間が長く、使わない筋肉があれば、衰えて硬くなるといいます。 そこを否定するつもりはありませんが、合気道をするのに困るほど可動域が狭いという人に出会ったことがありません。そのことに思い至って、硬いと
-
2021年12月8日


















