

ニューバランスのFresh Formで1万歩歩くとどうなるか
スニーカーの機能性に興味のなかった私が、靴のテクノロジーに無頓着なまま歩き続けると、足指が水ぶくれになったり、足のあちこちが当たって痛くなったりと。どうするよとなって、とりあえず良さそうかもと思ったのがFresh Formだったのです。
実はこの前に「合気道だけやっていても運動不
-
2024年12月15日


柔道で合気が使われないのはナゼ?
こんなことを聞かれました。
合気道の力の使い方が有効なら、どうして柔道の試合で、そんな技術が使われないのですかと、聞かれました。
ああー、ね(笑)
私は、こう答えました。
おひとりだけ歴史上、柔道の試合で合気道を使ったと言える人がいる。鬼の木村政彦に、合気道のおかげで勝ったと
-
2023年6月16日


武産合気って、合気道と何がちがう? 開祖は何を伝えようとされたのか
久しぶりに、合気道の用語です。今回も開祖の直弟子の方々の言葉を、書籍等から集めて解き明かしたいと考えています。斉藤守弘先生をメインに、植芝吉祥丸先生は若干、そして武産合気の概念らしきところは、田中万川先生や五味田聖二先生、塩田剛三先生の言葉から探っています。
なにより最も長く開祖
-
2023年5月13日


手が離れないのはどんな理屈?
合気道には、片手持ち、両手持ち、綾手持ち、諸手持ち、後ろ両手持ちなど手首を持たれる設定の技が数多くあります。やったことがない人が思う一番の疑問は、「なぜ離さない」「手を離せばいいんじゃない」ということではないでしょうか。
いや、そうそう。防ぐには離しちゃえばいいんです(笑)
-
2023年3月5日


『体はゆく』が提起する“できる”の道筋と身体のユルさ
『体はゆく』という本を読みました。驚異的に面白い内容です。
サブタイトル「できるを科学する<テクノロジー×身体>」に惹かれて読んでみたのですが、動く技能を取得するとは、どういうことなのか。
そこをあらためて考えさせられるだけではなく、自分が技を習得するのは、こういうメカ
-
2023年1月19日

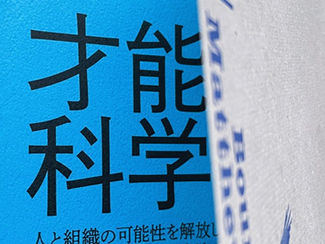
才能は遺伝? それともすべては後天的なのかという問いに
先天的な才能という概念自体が間違いで、ぜんぶ後天的なものだという主張が、異様な説得力をもって迫ってくる本です。
いやいや、そんなことないでしょうよ。
運動能力は千差万別。すぐに出来てしまう人もいれば、なかなか動作を覚えられない人もいる。そう思いながら読んだのですが、なんたって著
-
2022年11月26日


それじゃあ、どれだけ運動すればいいのか?
今回の話に登場するのは、ほぼリモートで仕事している人たちなんです。たまに出社するけれども、あとは在宅でほぼ座りっぱなし。
コロナ禍で何年もそんなスタイルだと特別に何かしないと、とんでもなく運動不足だし、身体の使われ方が偏っていると思います。
リモートじゃなくても、一般的に筋肉量は
-
2022年9月25日


腹圧をかけると体幹が強くなる?
先日の稽古中、ある女性に「ほら反り腰になってるよ」と注意する場面がありました。 すると意外な返事が。「腹圧をかけてるんですけど、ダメですか?」と。おお、腹圧をかけてる? 経緯はこうです。 なぜだか精晟会渋谷の女性会員は、整体などで反り腰だと言われた人が多いのです。反り腰とは骨盤の
-
2022年9月1日


誰でも同じような反応にならないのは、触覚の仕組みなのかも
「人の身体は千差万別。痛めつけないためにも効かせるためにも、相手に最適化した対応が必要」だと考えています。正確には身体そのものではなく、そのときの身体の状態ですが。
稽古が終わってから、「相手の身体がどうかって、どうやって知るんでしょう?」と聞かれました。掛け方ではなくそこか。
-
2022年7月8日


『反射が生む達人の運動学』は即買うべき。それぐらいに画期的な内容かと
私が書籍『反射が生む達人の運動学』に反応したのは、こんな3段階。
1.何より反射をこれだけまとめた本は、私が知る限り他にはない。
2.反射は身体に備わった自動的な仕組み。この参考書で研究すべし。
3.この手の本は、書店からは1年もせずに消える。後からAmazonで高い中古本を買い
-
2022年4月29日


体験の人が合気道に求めている思想性
求められそうなこと、聞かれそうなことは、できるだけ公開しているつもりです。ところがこのところ、体験で続けて予期していなかった興味をお聞きしました。
それが「合気道の精神を知りたい」「合気道の思想を知りたい」でした。
それはまったくと言っていいほど、このウェブサイトやブログでは触
-
2022年4月7日

合気道の合気って何? 力の概念なのか技術なのか理念なのか
合気道は文字通りに解釈すると、合気の道。しかしその「合気」とはいったい何でしょうか。
剣道なら、剣の道。真剣を使わなくても、竹刀を剣に見立てて稽古する武道であることに間違いないでしょう。
柔道は、やわらの道。やわらの辞書的な定義は「力で相手に対抗せず、相手の力を利用して逆に相手
-
2022年1月6日


合気道は剣の理合。なのに開祖はどうして剣を教えなかったのか?
さまざまな直弟子の先生方が「植芝先生は、合気道は剣の理合」だとおっしゃったとインタビュー等で答えられていますので、確実だと思います。
ただ、「それなのに一向に剣を教えてくれなかった」と続くのです。どころか、弟子が剣を使っていると「誰の許しを得た」と怒ったという話さえあります。
-
2021年10月30日


和製英語インナーマッスルの概念を提唱した整形外科医の話は目からウロコだった
肩の筋肉が内側と外側で異なる働きをしていることを解明。この内側の筋肉に「インナーマッスル」と名付け、学会で発表した整形外科医の筒井廣明先生が出演されていました。
私は五十肩ではないので、その治療自体に興味はありません。しかしインナーマッスルを正常に働かせる方法には、もちろん興味が
-
2021年9月30日


合気道のむすぶ・結びとは? どなたからも具体的な説明はないみたい
さまざまな雑誌や書籍、動画等で「むすぶ」「結び」「気の結び」が出てきます。ところが詳しい説明は、ほぼ見たことがありません。
詳しく説明しようとすればするほど、理屈で考えれば考えるほど、本質とはかけ離れてしまう概念はあると思います。それでもただただ「結ぶ」とか「むすび」とかいう言
-
2021年9月18日


合気道の気って何? どうにも統一見解はなさそうな気配
現代において武道の世界は特殊で、一般的にはあやしい存在でも、やっている人たちの中では当たり前とされていることは少なくありません。
合気道では、少なくとも「気」は、現在でもそのままに残り、受け入れられているのではないでしょうか。「気」をあやしいという合気道の人は、とても少ないと思
-
2021年9月2日


合気道には固い稽古と流れの稽古がある? その分岐点を辿ってみると
「固い稽古」「流れの稽古」というワードをよく目にしますが、養神館ではまず使われることのない言葉です。 想像すると、本来対立するような稽古方法ではないと思いますが、どうも譲れない主張があるようです。 最近も「出稽古に来た人の腕を掴んだら動けなかった」というツイ
-
2021年8月18日


合気道の力を抜くって? を具体的に探っていくと
合気道ではどこの流派でも「力を抜け」と、頻繁に言われていると思います。じゃあ、実際にどうやって力を抜けばいいのか、具体的にどういう状態のことかを教えられることはあるでしょうか。
「力を抜く」ことは重要なはずですが、書籍では、ほぼ言葉だけか、観念的な説明に終始しています。いくら重
-
2021年8月7日


合気道の当身って何? 消えてしまわないためのアーカイブへ
今回も合気道の用語です。言葉として「当身」はけっこう使われていると思いますが、実質的に合気道から当身は失われつつあるかもしれません。素手による当身がないのに、剣や杖、短刀を稽古し、それじゃ斬れないとか指導されているとしたら、かなり不思議な状況です。合気道は体術がメインのはずです。
-
2021年7月29日


合気道は円の動き。の奥のマニアックで難解な話へ
今回は、『円の動き』です。
合気道は円の動き、角がなく丸く動くなど、どこの合気道の道場でも言葉として「円」が高頻度で使われていると思います。
ところが植芝盛平先生は、私が知るかぎり書籍や映像で「円」という言葉は、それほど使われていないようです。
直弟子の先生方は、ご自分の解釈
-
2021年7月22日


















